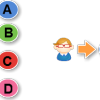「知っている」ということの重要性
今回はSNSを使う上でとても重要なポイント。「知っている」ということについて考えてみます。
プレゼンでは知らないことを話してもダメらしい
プレゼンやセミナーなど人前で話をする際、できればそこにいる方に色々な情報を持って帰って欲しいと思うのは別に変なことではないですが、問題はその量です。できるだけたくさんの情報を!と思ってみんなが知らない様な話ばかりをしてると逆にほとんど何も頭に入ってこないそうです。
・聴衆がすでに知っていること50%
・言われれば「聞いたことがあるな」と思い出すこと30%
・初めて聞く話20%
プレゼンのための5:3:2の法則-ライフハック心理学-
という感じで8割はみんなが知っている話で残り2割だけ誰も知らない新しい話にするぐらいの割合が一番いいそうです。
確かにいかに自分に興味がある分野だとはいえ、知らない話ばっかりされたらそりゃ退屈になってつまんないなと思ってしまうのも仕方ないですよね。
でもよくよく考えてみるとこれってプレゼンとかセミナーの話として考えるから意外だなと思うのであって他のことで考えてみれば至極、当たり前の話なんですよね。
例えば「歌」、例えば「ドラマ」などなど
これは別に最近になって始まったことではないですが、大分前に徳永英明さんを筆頭にカヴァーアルバムブームがありましたよね。歌番組は今でも懐メロばっかりやってます。
一部のメジャーなミュージシャン以外ではオリジナルの新曲を出してもなかなか注目されづらい現在、誰もが知っているヒット曲をカヴァーすることでニュースになり話題を集めるというのは「知っている」ことの重要性を上手く生かした手法ですね(カヴァーってそもそもそういったことのためにやるものではないですが、音楽評論ブログではないのでそれについては語りません)。
そしてドラマでも映画でも続編とかリメイクって多いですね。まったく新しいものをやるよりも多くの方が知っているものをベースにした方がとっつきやすいですしね。もちろん不景気で予算が少なく冒険できないという事情もあるのでしょうけど。
さらに歌、ドラマ以外でも例えばグリコの様々な復刻商品とかとにかく色々なものの復刻版が人気になってます。
不景気な時には新しいものにチャレンジして失敗するよりも大当たりはせずともそれなりの人気が見込める誰もが知っているものが多く出てくるってことですね。そしてそれを受け取る私達も「知っている」という安心感、親近感からついついそれに乗ってしまうと。
冒頭のプレゼンの話は別に不景気うんぬんは関係ないですけど、元々の人間心理の上にさらに不景気で人々はより「知っている」ということを重要視してるってのが今の時代の空気なのかなという感じです。
SNSでは「知っている」そして「知ってくれている」が重要
これまでAmazonのカスタマーレビューや食べログ、価格ドットコムなどの口コミが商品購入やお店選択にかかせないものとされていました。もちろん、それは今も変わりないのですが、それ以上にTwitterやFacebook、mixiなどの「知っている人のオススメ」というものがより重要となってきています。
専門家や評論家といった方の意見ならいざ知れず、まったく知らない他人の趣味、味覚など不確定要素の大きい情報よりも家族、友人など自分の知っている。そして自分のことを知ってくれている人の情報の方がより自分の好みに近いものをススメてくれるだろうということですね。
Amazonや食べログのレビューは
「知らない商品やお店の知らない人によるオススメ」
SNSでのレビューは
「知らない商品やお店の自分の、そして自分を知っている人によるオススメ」
と、こんな感じです。
何百、何千の友達、フォロワーがいたとしても結局、よくやりとりするのは決まった面子ですよね。そしてそこで色々なものをススメたりススメられたりすることが日常的になればなるほど、この「知っている」ということが重要になってくるし、逆に「知らない」ものにはなかなか手を伸ばしにくくなっていきます。
ここでのポイントは単に「知っている相手」ということではなく、「お互いに」知っているという部分ですね。
ただこのポイントはかなり重要で、自分の知らないものや情報であっても、家族、友人など自分が知っている人が知っている情報であればそれはもうほとんど自分にとっても知っているといって過言ではないってことなんです(なんか知っている、知っているばっかりでわかりにくいですね、すいません)。
安心感と親近感。そして説得力
今まで上げた話を無理やり合わせてみると…
自分の知っているミュージシャン 50%
自分の知っている曲 30%
そのミュージシャンと曲の組み合わせ 20%
実はここ最近、流行っていたカヴァー曲ってそのほとんどが既に何曲かのヒット曲を持った多くの方が知っているミュージシャンが歌っているものなんです。
新人さんや誰も知らないミュージシャンがいくら誰もが知っている曲を歌ったとしてもそれが話題になったり売れたりってのはなかなか難しいんです。何故ならそれだと上述した割合の30%しか満たしてないからです(誰も知らないミュージシャンが誰でも知っている曲を歌っても、そもそもその組み合わせが良いのか悪いのか誰にもわかりませんよね)。
誰もが知っているミュージシャン、誰もが知っている曲。この2つが合ってはじめて、聞き手に安心感と親近感が生まれます。これはつまりSNSの「お互いに知っている」という状態ですね。では残りの20%はと言うと、その組み合わせ、意外性です。
本当にたくさんのミュージシャンが色々なカヴァー曲を歌っていますが、その中でも売れる人もいれば、さっぱりな人もいる。上述した有名、無名というのがまずありますが、有名なミュージシャンであっても売れる人と売れない人がいる。その違いは何かといえば、あの人がこの歌を!という新鮮な驚きがあるかないかです。その組み合わせに面白みがなければどんなに頑張ったところで話題にはならない訳です。
ただ意外性は必要だけど意外過ぎてもいけない。その絶妙なバランスを一番、上手く取っていたのが、徳永英明さんなんだと思います。そしてその意外性をパーセンテージで表すと多分、20%ぐらいが丁度良い感じなのではないかなと。
「知っている」ということは相手に対して安心感と親近感を与えます。相手が自分に対して80%の安心感と親近感を持ってくれて初めて、後の20%の新しい情報に説得力が出ますし、信頼感を持ってちゃんと話を聞いてくれる様になる訳です。
既にたくさんのヒット曲を持っている。そして歌唱力のあるミュージシャンであると多くの人が「知っている」徳永さんだからこそ、一人ひとりがそれぞれ色々な思い出を持っている昔のヒット曲を歌っても、すんなりと受け入れられるし、徳永さんがこの歌を歌うとこうなるんだ!という20%ほどの驚きがより説得力を生み出し、彼に対するさらなる信頼感が出るのです。
みんなが知っている話をするのは自分を知ってもらうため
プレゼンやセミナーなど人前で話す時、聞いている方々はほとんどの場合、知らない人です。あなたがSNSでフォローしている、されている方々も必ずしも全員を知っている訳ではありません。
そういった中であなたの話をちゃんと聞いてもらうために80%は既に相手が知っている話をすると良いというのは、単に相手が知っている話をすれば良いということではありません。重要なのはそういった話をすることで自分を相手に知ってもらうということです。
自分をちゃんと知ってもらえればその後の話がとてもスムーズになりますし、相手もちゃんと聞く耳を持ってくれます。そうした上で残りの20%で新しい情報であったり、耳寄りな情報を伝えることができれば、相手はこれからもずっと継続してあなたの話を聞いてくれるようになります。
清志郎はこう歌っています。
誰かが僕の邪魔をしても
きっと君はいいこと思いつく
何でもないことで 僕を笑わせる
君が僕を知ってる何から何まで君がわかっていてくれる
僕のことすべて わかっていてくれる
離れ離れになんかなれないさ“君が僕を知ってる”
何でもないことで君を笑わし、離れ離れになんかなれなくなってしまう関係に友達、知り合い、フォロワーさんとなれるといいですね。
関連記事
-

-
Facebook広告ですぐに販売ページに誘導してはいけない理由
Facebookで情報を発信したり、広告を出したりしても思う様な結果が得られない場合、原因は
-
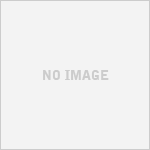
-
ほとんどの人に届かないFacebookページからの投稿
Facebookページリーチ激減り、ただ乗り終了のお知らせ-gizmodo今日、話題になってて色々な
-

-
情報発信の選択と集中
ネットで集客、販売したりお客様とコミュニケーションをとる上でTwitter、Facebook
-

-
バイラルメディアの全てが悪い訳ではないと思う理由
最近、ネット上でバイラルメディアに関する記事を良く見かけるようになりました。どちらかというと否定
-

-
情報隠しても意味ないし
これとか 作家や出版社側は、図書館で貸し出されなければ、その分購入する人々が増
-
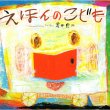
-
感動するストーリーにこだわる必要なんてない
コンテンツマーケティングを行う上でショップや店長、店員などのプロフィール。商品のヒストリーなんかをス
-
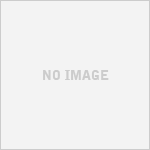
-
「わかりやすさ」の落とし穴
私は作詞家の立場で自分以外の人が歌う曲の歌詞を作る時と自分のバンドで自分もしくはメンバーが歌う歌詞を
-
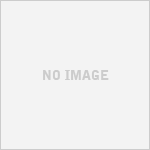
-
コミュニケーションはとにかくちゃんと手間をかけて
以前、あるテレビ番組が終わってしまったことに関して、「好きだったのに残念だな」とTwitterの個人
-

-
ブログで「愛」を伝えるということ
前回、ブログで集客する上で一番大事なのは「愛」を伝えることと書いた。でももうちょっと具体的にしな
- PREV
- コミュニケーションはとにかくちゃんと手間をかけて
- NEXT
- 「わかりやすさ」の落とし穴